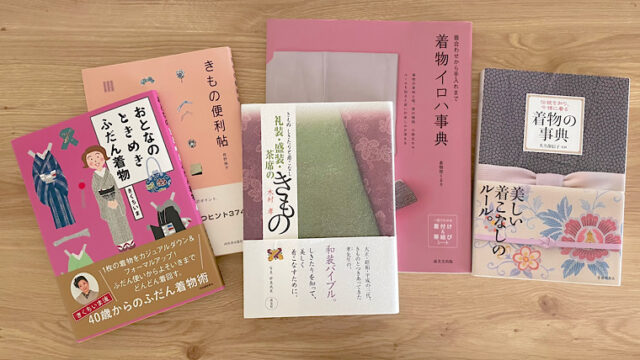【着物好きのおすすめ6選】着物の着る機会が多くなる習い事

Contents
着物を着れる和の習い事がおススメの理由
着物を着る回数が増える
大好きな着物も着る機会がないと、どんどん着付けが下手になってしまうし、何年も箪笥の中にしまったままなんて残念なことになりかねません。
そんな時は和の習い事を始めませんか?
着物に関係のある習い事にふれると、着る機会がどんどん増えます。
しかも、着物を着る回数が増え所作も体に馴染んできます。
自然と着物姿も美しくなってきて、いい事ずくめ。
着物好きな仲間と出会える

和の習い事は着物が大好きな方が多く集まりますので、自然と着物に関係する話題も増え着付けのコツやお出かけ情報も増えてきます。
習い事をしているうちに和の情報も増え、日本文化への興味もどんどん深くなります。
着物を着る機会のある習い事オススメ6選
着付け教室

着付けは自分が着るだけではなく、他人を着せる他装ということもできます。
私の周りにも 着物は着たいのだけど、着れないからあきらめるという方が多くいます。
また体型によっても着付けのポイントがかわってくるそうなので、いまいち着物姿が決まらないと思っている方は、基本からお勉強するのも良いかもしれません。
きもの着方教室のいち瑠![]() さんでは、入会前に無料体験レッスンを受けられるので教室の雰囲気を知ることができますから、自分に合うか合わないかを確かめてから始められます。
さんでは、入会前に無料体験レッスンを受けられるので教室の雰囲気を知ることができますから、自分に合うか合わないかを確かめてから始められます。
浴衣から紬、柔らか物までお稽古で着ることができる。着物を着る回数も断然多い。
日本舞踊

着物を着る習い事の1番はやはり日本舞踊でしょう。日本舞踊の魅力は、着物の美しい所作や動きにありますから、その立ち振る舞いが身に付きます。
そもそも洋服から浴衣に着替えなければその日のお稽古が始まりません。
お教室によっては、着付け教室から行なっているところもありますので、動いても崩れない着物の着付けを教えていただけるのは魅力です。
浴衣はお稽古で必ず着る。衣装として普段着ることができない着物が着れる。
茶道

着物を着ることが多い茶道はお教室の先生にもよりますが、お洋服OKのお稽古場所もあります。
ただ時間があれば着物を着て、お稽古に行くのが1番です。
お稽古の時は、抹茶の粉を落とすことがありますので、色の濃い普段着物か洗える着物が良いでしょう。
また茶道は流派によってお手前が少しずつ違いますので、習う前に各流派について少し調べていかれると良いかもしれません。一度習い始めたら一生のおつき合いになり、途中から流派を変えるというのはなかなか難しくなります。
茶道は主に千利休から始まった表千家、裏千家、武者小路千家があります。
表千家、武者小路千家、は各お教室ごとで探す必要がありますが、裏千家はHPがありますのでこちらから検索してみると探しやすいかも。裏千家お教室案内
お稽古は、紬や小紋などの普段着物。お茶会の時は色無地や訪問着など幅広く着る。
華道

花を生ける時は洋服のことが多いですが、作品展の時にお友達を着物でお迎えすると素敵ですね。
季節の花と空間をデザインする華道は美的センスも磨かれますし、一年を通してお稽古すると花の名前も覚えてしまいます。
持ち帰ったお花を部屋に飾ることで部屋の中が生き生きしてきますね。いけたお花のつぼみが咲くと感動してしまいます。
華道は流派が細かく分かれていて、その中でも日本の代表的な流派は、池坊、草月流、小原流があります。それぞれ特徴がありますので、どこの流派にしたらいいか迷った時、デパートや公民館などで行われている作品の展示イベントに行ってみると良いでしょう。
お教室では洋服が多い。展示イベントなどで着ることがある。
琴

日本の楽器と着物の相性が良いのはやはりお琴でしょうか。定期的に行われる発表会のお着物姿は、見ている方も琴の音を聞きながら見入ってしまします。普段の練習はお洋服の所が多いようです。
お琴は年齢に関係なく大勢で演奏できるのも魅力です。
お教室では洋服が多い。発表会などで華やかな着物を着たりする。
お能(謡・仕舞い)

初めてお能のお稽古ができると知った時は驚きました。関東圏にも多くのお稽古場があります。
また、狂言のお稽古場もありますから、探してみてくださいね。
私の先生は、いつも着物に袴姿で教えてくれました。生徒さんは仕舞いのお稽古の時は体の軸が見えるから服の方がいいんだって。
謡のお稽古で着物でいらっしゃる方はいます。私は鎌倉能舞台でお稽古してました。
流派があるのに加え先生もプロの舞台を踏む先生から、素人の先生まで多くいらっしゃいます。流派についてはワゴコロさんのサイトを参考にしてみてください。
先生の探し方については、まず舞台を見に行ってお気に入りの能楽師を探すことが1番かと思います。
お教室では洋服が多い。発表会には袴や、格の高い紋入りの着物を着る。
着物を着る習い事まとめ

その他にも和の習い事はたくさんあります。三味線や煎茶道、書道に俳句、香道などなど。比較的高齢になっても続けられるものが多いのが魅力です。
和の香水、塗香を作れたりするお教室もありますよ。
(写真 妙香寺香宮堂お香教室)
ご自分に合った習い事を見つけて、お稽古を始めることで着物を着る機会も増えるのではないでしょうか?
ちなみに私は、茶道とお能(謡、仕舞い)のお稽古を50歳付近で始めて、付かず離れず?の着物生活を楽しんでいます。